|
|
妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援 主な目標:
|
|
周産期・新生児・妊産婦死亡率の推移
a;出産千対,b;出生千対,c;出産10万対
|
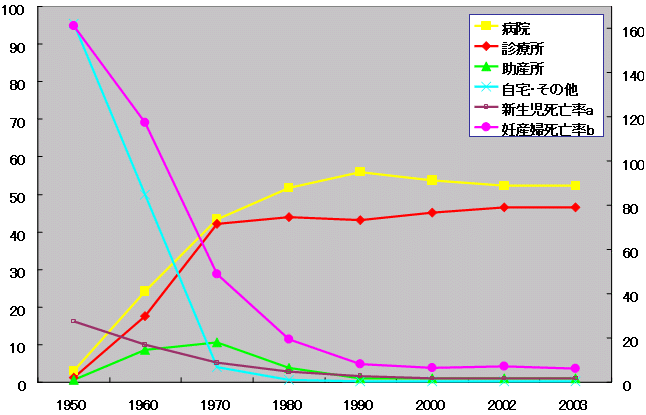
(平成15年)
| 出生場所 | 出生数 | 割合(%) |
| 病院 | 586,000 | 52.2 |
| 診療所 | 524,118 | 46.6 |
| 助産所 | 11,190 | 1.0 |
| 自宅・その他 | 2,302 | 0.2 |
| 合計 | 1,123,610 | 100.0 |
| 都道府県別出生の場所別にみた出生百分率の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療所分娩の割合 | 平成4年 | 平成14年 | 平成15年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40%以下 | 13 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50〜40% | 19 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50%以上 | 15 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国名 | 年 | 妊婦死亡率 出生 10万対 |
新生児死亡率 出生 千対 |
周産期死亡率 出生 千対 |
総医療費/GDP の世界順位 |
| 日本 | 2003 | 6.1 | 1.7 | 3.6 | |
| 1999 | 6.1 | 1.8 | 4.0 | ||
| 1998 | 7.1 | 2.0 | 4.1 | 17位 | |
| 1997 | 6.5 | 1.9 | 4.2 | ||
| アメリカ | 1999 | 4.7 | 1位 | ||
| 1998 | 7.1 | 5.1 | |||
| フランス | 1999 | 2.9 | 5位 | ||
| 1998 | 10.1 | ||||
| 1997 | 2.7 | 7.1 | |||
| スウェーデン | 1998 | 7.9 | 2.3 | 5.2 |
(全国 平成14年)
| 産婦人科 | 10,616 |
| 産科 | 416 |
| 婦人科 | 1,366 |
| 助産師数 | 24,340 |
(全国 平成14年)
| 産婦人科病院 | 1,590 |
| 産婦人科診療所 | 3,282 |
| 産科病院 | 213 |
| 産科診療所 | 658 |
| 助産所 | 730 |
(平成15年)
| 就業場所 | 人数 | 割合(%) |
| 保健所 | 216 | 0.8 |
| 市町村 | 437 | 1.7 |
| 病院 | 17,684 | 68.7 |
| 診療所 | 4,534 | 17.6 |
| 助産所 | 1,601 | 6.2 |
| 社会福祉施設 | 15 | 0.1 |
| 事業所 | 12 | 0.0 |
| 看護師等学校養成所等 | 1,020 | 4.0 |
| その他 | 205 | 0.8 |
| 合計 | 25,724 | 99.9 |
(平成17年)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | |
| 医師 | 8,795 | 7,568 | 89.1 |
| 保健師 | 9,134 | 7,440 | 81.5 |
| 助産師 | 1,624 | 1,619 | 99.7 |
| 看護師 | 48,299 | 44,137 | 91.4 |
| 助産師数別分娩機関数(平成14年厚労省統計情報部) |
|||||||||||
| 助産師数 | 1人未満 | 1〜4.9 | 5〜 | 合計 | |||||||
| 病院数 | 56 | 324 | 1123 | 1503 | |||||||
| 割合(%) | 3.7 | 21.6 | 74.7 | 100 | |||||||
| 診療所数 | 586 | 1112 | 105 | 1803 | |||||||
| 割合(%) | 32.5 | 61.7 | 5.9 | 100 | |||||||
|
|||||||||||
| 助産師の卒業後の就業状況(平成16年3月) |
||||
| 助産師としての就業 | ||||
| 病院 | 診療所 | その他 | 計 | |
| 大学 | 275 | 2 | 3 | 280 |
| 短大・養成所 | 1033 | 28 | 2 | 1063 |
| 計 | 1308 | 30 | 5 | 1343 |
| 割合(%) | 97.4 | 2.2 | 0.4 | 100 |
2005年8月31日 37県医会支部統計
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 合計 | 合計 | |||||
| 病院 | 診療所 | 病院 | 診療所 | 病院 | 診療所 | 病院 | 診療所 | ||
| 新規開設 | 5 | 23 | 4 | 10 | 6 | 25 | 15 | 58 | 73 |
| 分娩とりやめ | 13 | 48 | 25 | 76 | 38 | 71 | 76 | 195 | 271 |
| 減少数 | 8 | 25 | 21 | 66 | 32 | 46 | 61 | 137 | 198 |
| 病院 | 診療所 | |
| 分娩医療機関数 | 885 | 1,330 |
| 減少数 | 61 | 137 |
| 減少率 | 6.9% | 10.3% |
(茨城県)
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | |
| 実績(人) | 27,926 | 27,659 | 26,751 | 6,267 |
| 実施医療機関数 | 94 | 88 | 83 | 76 |
| ※ | 平成17年度実績は中間データです。 |
|
産科医の減少 分娩医療機関の減少 助産師の超不足 |
1分娩機関あたり助産師6〜8人が必要
|
狭義:胎児娩出、広義:陣痛から胎児・胎盤娩出
| 分娩経過 | 所要時間 | ポイント | 担当 | |
| 分娩I期 | 陣痛期 | 8時間 | 観察 | 医師・助産師・看護師 |
| 分娩II期 | 胎児娩出 (子宮口全開〜児娩出) |
50分 | 娩出介助 | 医師・助産師 |
| 分娩III期 | 胎盤娩出 | 5〜10分 | 医師・助産師 | |
| 分娩IV期 | 回復産褥早期 | 2時間 | 観察;出血・一般状態 | 医師・助産師・看護師 |
| ☆ | 分娩介助:
|
||
| ☆ | 助産:
|
||
| ☆ | 看護:
|
|
|||||||||||
周産期医療には医師・助産師・看護師の連携が不可欠
|
|
助産師の絶対的不足状況を放置→→周産期医療の崩壊 直ちに助産師を増加させる有効な処置を施す 助産師不足への対応 現状を見据えた対応 助産師が充足するまでの間、看護師に助産を教育(公的に) 将来を見据えた対応 助産師を必要数多数養成 看護師養成カリキュラムに、助産に必要な知識・技能の項目 看護師に内診も含む助産行為ができるようにする。 (産科エキスパート・ナースの養成) |
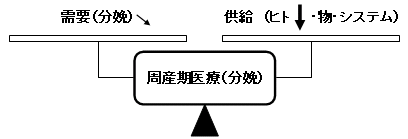
|
助産師超不足、産科医減少→産科診療所閉鎖 →妊婦が一部の分娩機関に集中→病院産科閉鎖 →周産期医療の崩壊→少子化の加速 助産師の増員(緊急的課題) 看護学校で助産を修得したいわゆる 「産科エキスパート・ナース」を養成する 医療機関内(医師の指示)の助産師・看護師の役割 助産師が充足されるまでの暫定的対応 |
分娩経過における観察・計測・操作と難易度・危険性
|
|
|
「保健師助産師看護師法の解説」(日本医事新報社刊) 看護とは 健康を主体とする人間の健康保持増進、疾病予防、分娩にともなう必要な処置と前後の世話など生命を守り、これを延長することのために役立つもの |
|