| 厚生労働省発表 平成18年10月31日 |
|
市町村域での要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止を目的とする
ネットワークの設置状況調査の結果について(平成18年4月調査)
【調査目的】
| 平成16年の児童福祉法の改正により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)域における児童虐待防止に向けた取組は、これまで以上に重要なものと位置づけられたところであり、さらに、児童虐待防止ネットワークについては、要保護児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う「要保護児童対策地域協議会」として児童福祉法に位置づけられたことから、市町村域での要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワークの設置状況等を把握し、より効果的な施策の検討に資するため、調査を実施した。 |
【調査方法】
全国1,843市町村を対象に、平成18年4月1日現在における、要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワークについて、主として以下の項目の質問を行った。
|
【調査結果】
別紙のとおり
|
| (1) | 要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワーク設置状況(表1、図1) 平成18年4月1日現在において、児童福祉法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)と児童虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置済みの市町村は、全国1,843市町村の69.0%にあたる1,271か所となっており、全国の約7割で協議会又はネットワークが設置されている。 また、平成18年度中に協議会又はネットワークの設置を予定している市町村は277か所(15.0%)であった。 なお、平成13年度以降の協議会又はネットワークを設置済みである市町村の数及び割合は、図1のとおり、増加している。 |

| (2) | 協議会及びネットワークの設置状況の詳細(表2) 平成18年4月1日現在において、協議会を設置済みである市町村は、全国1,843市町村の32.4%にあたる598か所であった。 また、ネットワークを設置済みである市町村は、全国1,843市町村の36.5%にあたる673か所であり、このうち、協議会へ移行を予定している市町村 は356か所であった。 |
| 表2 | 要保護児童対策地域協議会及び虐待防止ネットワークの設置状況 |
(平成18年4月1日現在)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (参考) | 要保護児童対策地域協議会の設置状況 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 協議会設置予定及び協議会設置していないには、ネットワーク設置済みも含む。 |
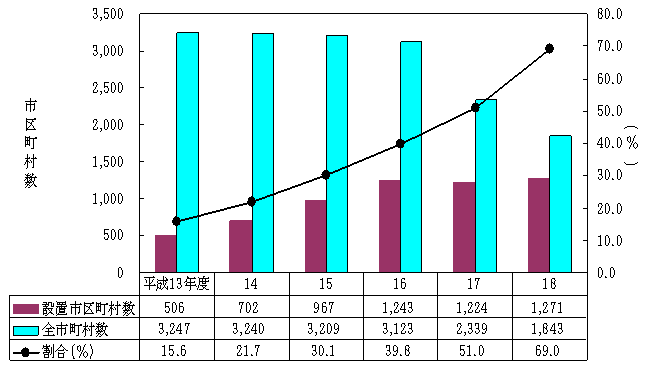 |
| * | 同時期の全国の市町村数に占める割合。 |
| 注) | 平成17年度までは6月1日現在の調査であり、18年度については4月1日現在の調査である。 平成16年度まではネットワークの設置数及び割合であり、17年度からは協議会又はネットワークの設置数及び割合である。 |
| (3) | 都道府県ごとの協議会又はネットワーク設置状況(表3) 協議会又はネットワークの設置済の市区町村の割合を都道府県ごとにみると、最低で26.2%、最高で100.0%となっている。 全体では、20〜40%未満が4県(8.5%)、40〜60%未満が12府県(25.5%)、60〜80%未満が14都県(29.8%)、80%〜100%未満が11道県(23.4%)、100%が6府県(12.8%)となっている。 |
| 表3 | 都道府県ごとの協議会及びネットワークの設置済み市町村の割合 |
| (平成18年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ○ | 協議会又はネットワークの設置目的(表4) 協議会又はネットワークの設置目的を「発生予防」、「早期発見・早期対応」、「保護・支援」の3つに分けて調査したところ、「早期発見・早期対応」が1,264か所(80.2%)と最も多かった。次いで、「発生予防」が1,129か所(71.6%)であった。 さらに、929か所(58.9%)のネットワークは、「発生予防」から「早期発見・早期対応」、「保護・支援」まですべての目的を有していた。 |
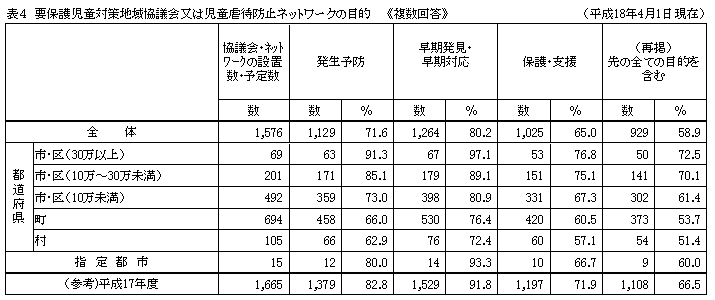
|
| ○ | 協議会又はネットワークの児童虐待防止以外の業務分野(表5) 協議会又はネットワークの児童虐待防止以外の業務分野は、「不登校」472か所(29.9%)、「非行対策」420か所(26.6%)、「障害児支援」365か所(23.2%)、「ひきこもり」362か所(23.0%)の順に多くなっている。 |
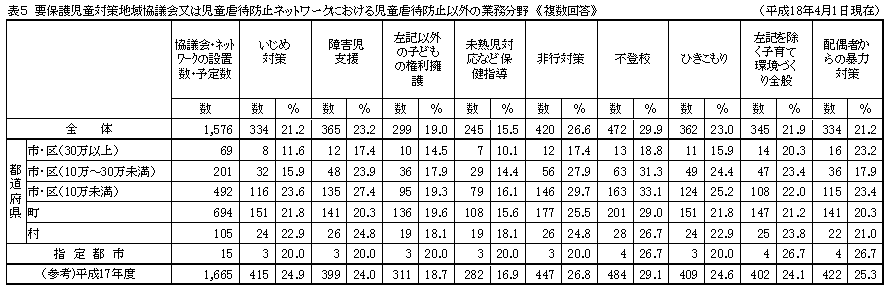
|
| 協議会又はネットワークを設置したことによるメリットや効果、改善された点等を調査したところ、「連絡調整や情報共有がスムーズになった」1,029か所 (65.3%)と最も多く、次いで「虐待問題の認識・関心が高まった」937か所(59.5%)、「各関係機関の役割が明確になった」768か所(48.7%)、「早期介入ができるようになった」643か所(40.8%)となっている。(表6) |
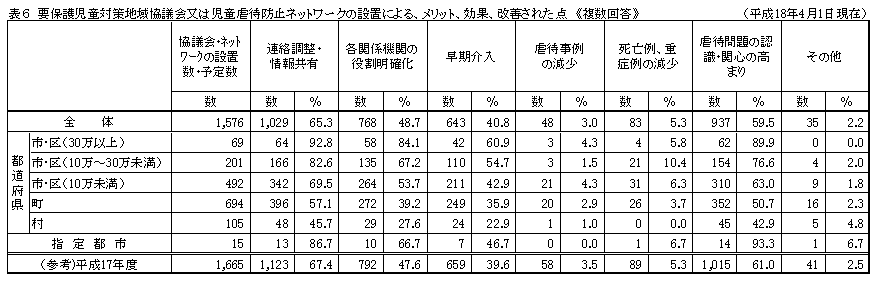
|
| 協議会又はネットワークの活動上の困難点を調査したところ、「事務局に負担が集中してしまう」585か所(37.1%)、「スーパーバイザーがいない」が585か所(37.1%)、「効果的な運営方法が分からない」が551か所(35.0%)となっており、技術的な運営の困難さが指摘されている。(表7) |
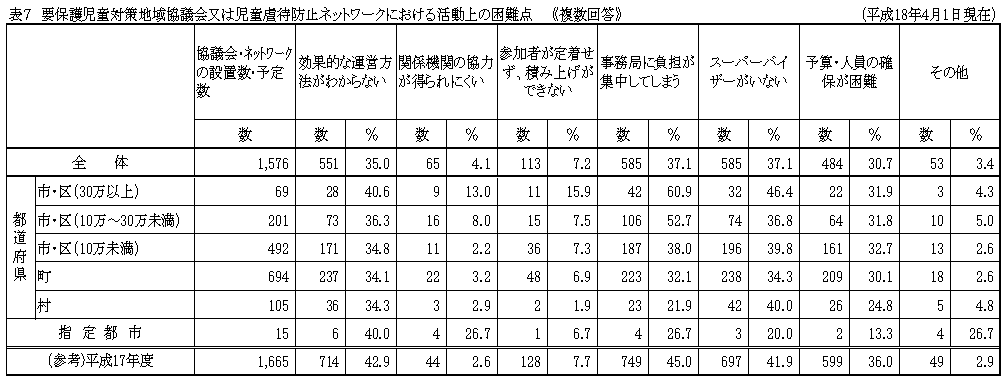
|
| 活動上、特に工夫している点を調査したところ、以下のとおりであった。 |
| 工夫点 | |||||||||||||||||
| 活動全般 に関すること |
|
| 会議の運営 に関すること |
|
|
| 協議会又はネットワークの機能充実のための課題を示すと、以下のとおりである。(表8) 「効果的な会議のあり方の工夫が必要」が892か所(56.6%)と最も多く、次いで「関係機関に対する虐待防止の意識付けが必要」としたところが747か所(47.4%)、「児童相談所と関係機関の役割の明確化が必要」としたところが631か所(40.0%)となっている。 「専門職の雇用等、人材確保が必要(職種等)」としたところは601か所(38.1%)となっており、具体的には、児童福祉司、社会福祉士、カウンセラー等の心理職、医師、保健師、弁護士等の確保が必要という意見が多かった。 |
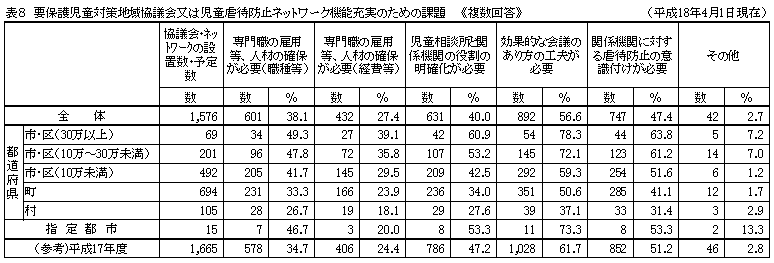
|
| (1) | 協議会を設置していない理由(表9) 協議会を設置していない市町村について、その理由を調査したところ、「調整機関のコーディネーターの人員確保が困難」(44.4%)、「地域協議会のリーダー的役割を担う人材確保が困難」(40.6%)といったような人材確保の困難を理由とするものが多かった。 また、「予算確保が困難」(31.9%)、「設置、運営の手法がわからない」(20.8%)といった理由が続いている。 これに対し、「各機関の通常業務で要保護児童対策への対応可能」(39.3%)、「子育て支援ネットワークなどで対応可能」(25.9%)といったような既存の体制で対応可能という理由も見られている。 |
| 表9 | 要保護児童対策地域協議会を設置していない理由《複数回答》 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ネットワークを設置していない理由(表10) ネットワークを設置していない理由については、協議会と同様の理由であった。 具体的な数値については、以下のとおりである。 |
| 表10 | 虐待防止ネットワークを設置していない理由《複数回答》 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (1) | 協議会の設置形態(表11) 協議会の設置形態について調査したところ、「1つの市町村に1つ設置」としているところが殆どであり、1,200カ所(98.2%)となっている。 |
| 表11 | 要保護児童対策地域協議会の設置形態 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ネットワークの設置形態(表12) ネットワークの設置形態には、協議会と同様の設置形態であった。 |
| 表12 | 児童虐待防止ネットワークの設置形態 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (1) | 協議会の調整機関(表13) 児童福祉法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)の設置について調査したところ、「調整機関を設置済」が1,185か所(97.0%)であった。 調整機関の回答では、児童福祉主管課(母子保健統合主管課を含む。)が多かった。 |
| 表13 | 要保護児童対策調整機関の指定状況 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (参考) | 児童虐待防止ネットワークの中核機関 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 調整機関におけるコーディネーターの配置状況(表14) 調整機関に常勤職員のコーディネーターを配置しているのは358か所(59.9%)、非常勤職員のみを配置しているのは74か所(12.4%)であった。 |
| 表14 | 要保護児童対策調整機関におけるコーディネーターの設置状況(協議会設置済市町村) |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 協議会に課せられた守秘義務の効果(表15) 協議会に課せられた守秘義務の効果については、「機関間の情報提供・収集がしやすくなった」が588か所(48.1%)、「特に変化なし」が519か所(42.5%)、「さらに改善すべき点がある」と回答したのは48か所(3.9%)であった。 |
| 表15 | 要保護児童対策地域協議会に課せられた守秘義務の効果《複数回答》 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
協議会又はネットワークについて、関係機関等がどの程度の率で参加しているかをみると、教育委員会、児童相談所、保育所、民生・児童委員協議会、警察署、小中学校の参加率が高かった。(表16,図2)
|
| 表16 | 要保護児童対策地域協議会又は児童虐待防止ネットワークを構成する関係機関及び割合《複数回答可》 |
(平成18年4月1日現在)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 指定都市においては、市設置の児童相談所を計上している。 |
| ※2 | 指定都市・特別区・保健所政令市においては、市区設置の保健所を計上している。 |
| ※3 | 個人参加の保健師等とは、保健師・助産師・看護師の看護職をあわせたもの。 |
(平成18年4月1日現在)
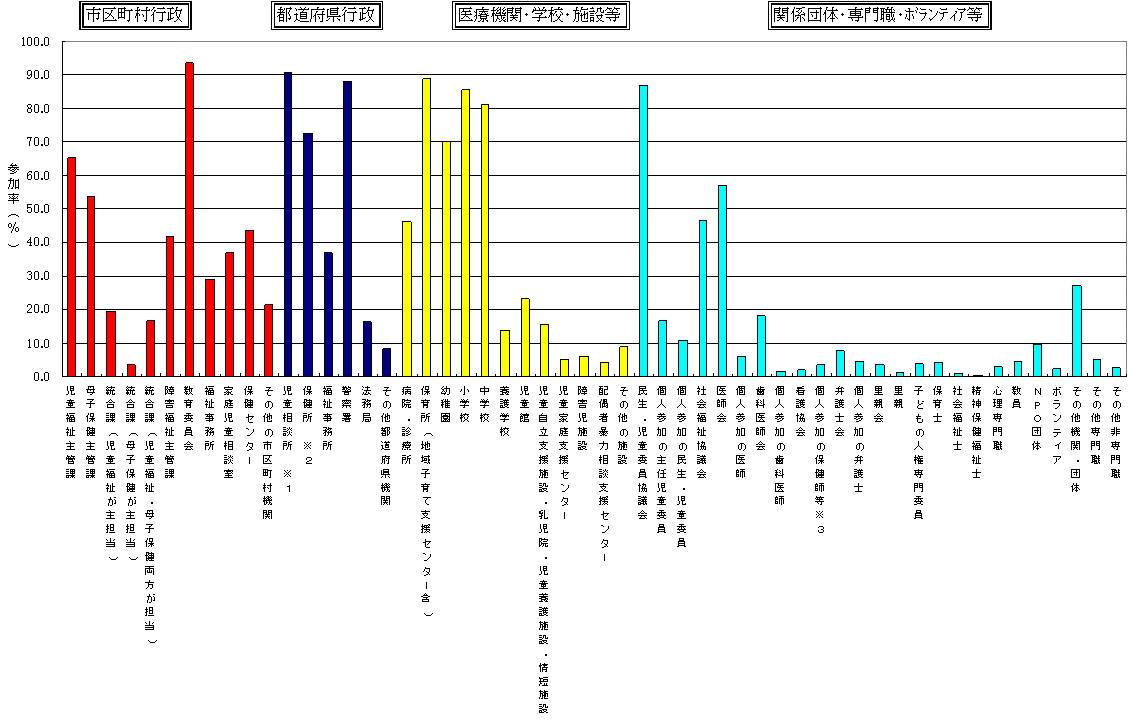
|
|
| (1) | 機関連絡会議の開催(表17) 代表者会議の開催は1,006か所(63.8%)、実務者会議の開催は920か所(58.4%)、個別ケース検討会議は1,151か所(73.0%)で、個別ケース検討会議が最も多く開催されていた。(表17−1、17−2、17−3) 開催時期は、代表者会議については、定期開催が604か所(38.3%)、不定期開催が397か所(25.2%)であったが、実務者会議では定期開催が427か所(27.1%)、不定期開催が484か所(30.7%)、個別ケース検討会議では定期開催が107か所(6.8%)、不定期開催が1,035か所(65.7%)となっており、実務的な会議になるに従って随時開催されている。 会議の開催回数は、代表者会議では、年1回が663か所(42.1%)であり、年2〜3回と併せると61.2%となっている。実務者会議では、年1〜4回が581か所(36.9%)であり、年5〜12回の開催も263か所(16.7%)あった。個別ケース検討会議では、年1〜6回の開催が532か所(33.8%)、年7〜12回が235か所(14.9%)、年13回以上も256か所(16.2%)あった。 |
| 表17 | 要保護児童対策地域協議会又は児童虐待防止ネットワークにおける機関連絡会の開催状況《複数回答》 |
| 表17−1 | 代表者会議の開催 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表17−2 | 実務者会議の開催 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表17−3 | 個別ケース検討会議の開催 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 研修会等の開催(表18) 協議会及びネットワークの活動内容のうち、「研修会」は577か所(36.6%)、「保護者・住民等への講演会・学習会」が248か所(15.7%)で実施されていた。その他の活動としては、リーフレットの作成・配布等を通しての普及啓発活動が大部分であった。 |
| 表18 | 要保護児童対策地域協議会又は児童虐待防止ネットワークにおける研修等の開催状況《複数回答》 |
| 表18−1 | 研修会の開催 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表18−2 | 保護者・住民を対象にした講演会・学習会 |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表18−3 | その他(リーフレットの配布等) |
(平成18年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||