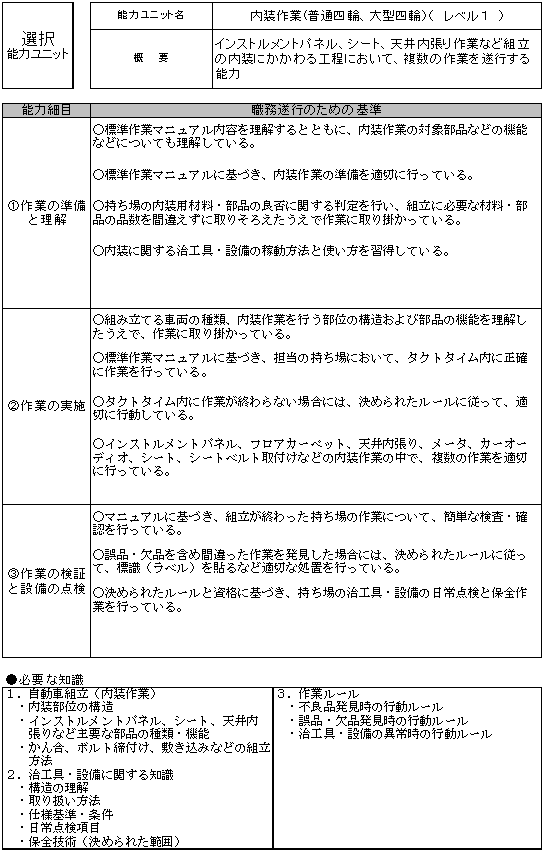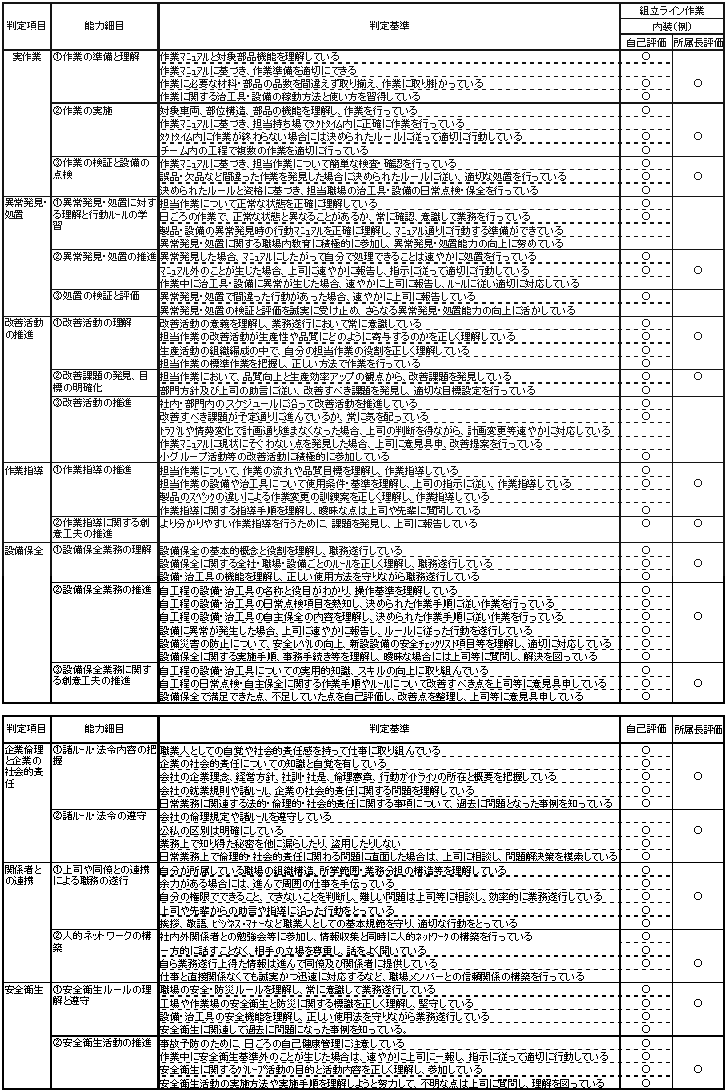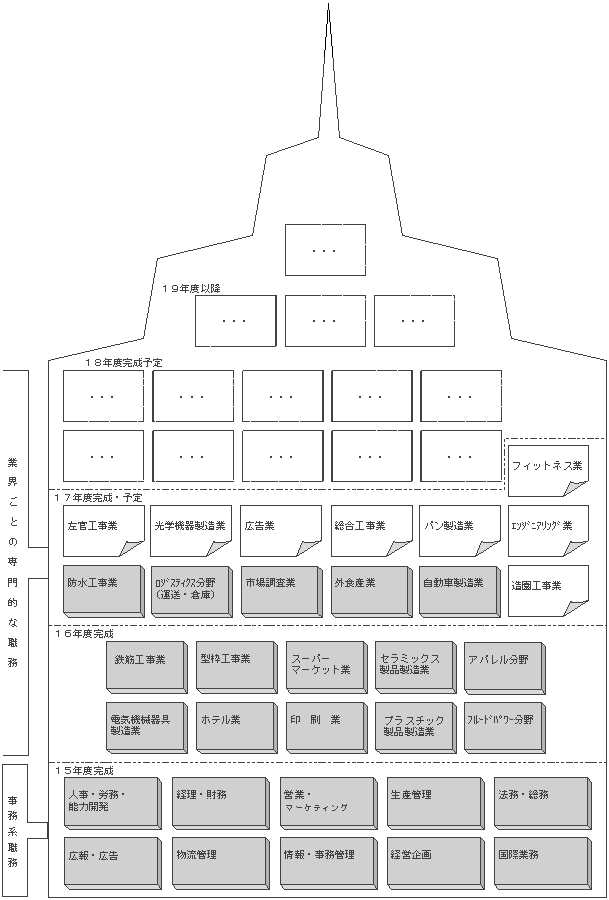|
|
〜採用や人事評価に活用できる「能力診断シート」を併せて作成〜
(ポイント)
[中央職業能力開発協会 http://www.hyouka.javada.or.jp]
|
| 1 | 能力評価基準の策定までの経緯 |
| (1) | 自動車製造業(「組立」職種)については、(社)日本自動車工業会(会長・小枝 至)及び全日本自動車産業労働組合総連合会(会長・加藤 裕治)との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・藤本 隆宏 東京大学COEものづくり経営研究センター センター長、東京大学大学院 経済学研究科 教授)を設置し、検討を行った。 | ||||||||||
| (2) | 同委員会は、職種選定にあたり調査を実施し、
|
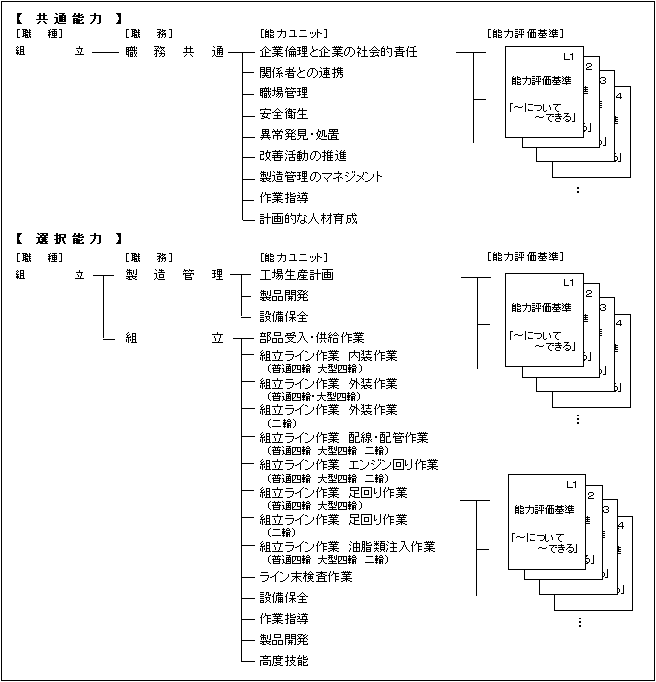
| 2 | レベルの設定 能力評価基準の策定に当たっては、これが職業能力を評価する基準であると同時に、労働者にとってキャリア形成上の指針となるように、役職等とそれに必要とされる職業能力の関係の実態に照らし、担当者に必要とされる能力水準(レベル1)から組織・部門の責任者に必要とされる能力水準(レベル4)まで4つのレベルを設定した(図2参照)。
上記の能力評価基準全体に共通するレベル区分の考え方に沿いながら、より具体的にイメージできるよう、自動車会社各社へのアンケート及びヒアリング調査の結果も踏まえ、自動車製造業(「組立」職種)におけるレベル区分の目安を設定した(図3参照)。 |
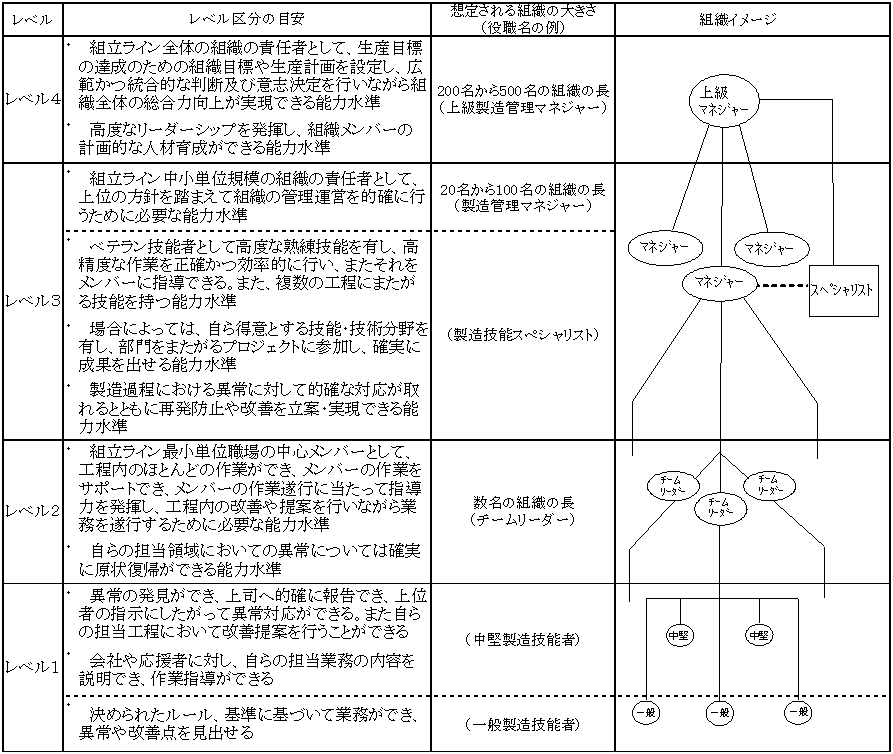
| ※ | 役職名称及び想定される組織の大きさは企業ごとに異なるため、参考例として示している。 |
| 3 | 活用例:能力診断シート |
| (1) | 策定された能力評価基準が実際に有効的に活用されるためには、具体的な評価手法をどのように設計・実施するかが重要な課題である。 従って、本委員会では能力評価基準の企業における様々な活用事例の一つとして、能力評価基準のユニット内容を基にした「能力診断シート」をとりまとめた(図4、図6参照)。 |
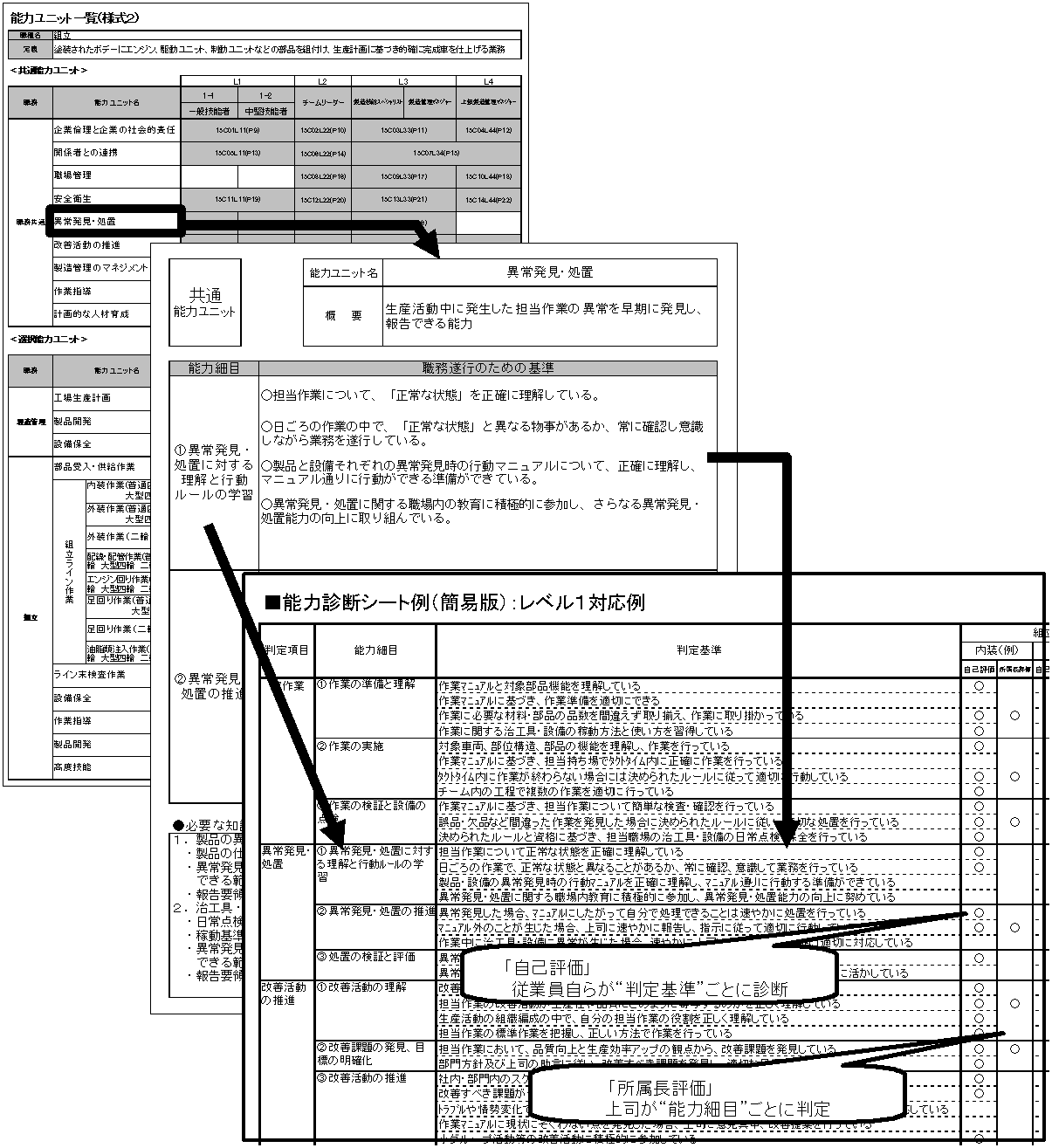
(診断方法)
| ・ | 各診断項目の判定基準別に「できる」または「やっている」と思われるものに○を付ける方法(2段階評価)としている。 |
| ・ | 従業員自らが行う自己評価部分は”判定基準”ごとに診断し、所属長が行う診断は利便性を考慮し、各判定基準のまとまりである”能力細目”ごとに判定する。 |
| (2) | 想定される活用場面 「能力診断シート」は、従業員の能力を診断・評価する際に各社の実態に即した評価手法を検討する素材であり、今後、人事評価や採用場面での活用が期待されるものである。
|
| 4 | 能力評価基準を活用するメリット 能力評価基準が明らかになることによって、的確なキャリア形成を図ることができる環境が整備され、また、職業能力に関するミスマッチが縮小することが期待される。 |
| (1) | 求職者・労働者にとっては、職業選択やキャリア形成の目標を立てる際に、(1)自らの能力の客観的な把握、(2)企業が必要とする能力の把握が可能となり、職業能力の向上に向けた取組みにつなげることができる。 |
| (2) | 企業にとっては、人材に関する企業戦略を立てる際に、採用すべき人材の明確化、人材育成への効果的な投資、能力に基づいた人事評価・処遇等の導入・定着に関する新しいスタンダードとして活用できる。 |
| (3) | ハローワーク等の労働力需給調整機関にとっては、労働者、企業の双方が職業能力を明確に示すことにより、雇用のミスマッチ解消につなげることができる。 |
| (4) | 教育訓練実施機関にとっては、職業訓練の対象者の能力レベル表示や修了時の能力評価を適切に行うことができる。 |
| 5 | 今後の事業の取組み 現在、広告業、造園工事業等について、能力評価基準の策定作業を進めているところである。今後も引き続き、幅広い分野について能力評価基準の整備を行うこととしている(図7参照)。 |
| 6 | 「職業能力評価制度整備委員会活動報告書」及び「能力評価基準」の入手先 |
|